こんにちは、ベトナム株投資アドバイザーのベトテク太郎です。
ハノイで生活していると、市場の物価変動を肌で感じる機会が多いんですよ。特に野菜や肉の価格が急騰したとき、「社会主義のベトナムにおいて誰がこの価格を管理してるんだろう?」って思ったことありませんか?
実は今、ベトナム政府がその「物価安定化」の責任を、これまでの県レベル(cấp huyện)から村・町レベル(cấp xã)に移そうとしています。一見すると「現場に近い方がいいじゃん」って思うかもしれない。でも、ハノイに12年住んでる僕から見ると、この改正案、かなり現実離れしてるんです。
政府が進める「物価安定化」の地方分権化
10月9日、ベトナム国会常務委員会で「価格法」の改正案が審議されました。この改正案の目玉が、物価安定化プログラムの実施責任を県レベルから村・町レベルに移管するという内容です。この情報から、ベトナムの行政区分について理解できました。2024年7月1日から「二層制」が導入され、県レベル(cấp huyện)が廃止され、省・直轄市(cấp tỉnh)と村・町レベル(cấp xã)の二層構造になったことが背景にあります。
では、財務大臣ニュエン・ヴァン・タン氏の発言を見ると、「県レベルが活動を終了したため」村レベルに物価安定化の責任を移すとしています。でも、国会常務委員会の多くのメンバーが懸念を示しているのが、村レベルの人員不足です。
内務省の2024年報告によると、1つの村あたり平均でわずか0.6人の専任財務会計担当者しかいないそうです。これで物価安定化という複雑な業務を担当できるのか?
正直なところ、ハノイに12年住んでて、この改正案には首をかしげざるを得ないんですよ。
現場を知る者としての違和感
ハノイの街を歩いていると、村レベル(xã)の行政事務所がどれだけ小規模かよく分かります。窓口は数人、パソコンは古い機種、そして財務担当者は1人か2人。そんな彼らに「物価安定化プログラムの実施」を任せるって、現実的でしょうか?
物価安定化って、単に「価格を決める」だけじゃないんです。市場調査、需給バランスの分析、関連業者との調整、補助金の配分、そして効果検証…こんな専門性の高い業務を、0.6人の財務担当者に押し付けるのは無理がある。
国会常務委員会の懸念──現実を見据えた指摘
国会常務委員会の委員たちの発言を見ると、現場の実態を理解している人が多いことが分かります。
**ニュエン・タン・ハイ氏(国会代表活動委員会委員長)**の指摘は特に的確です。「村レベルへの権限移譲は、人員不足という厳しい現実に直面する可能性がある」と。彼女は、村レベルが業務を担えない場合は省レベルが担当すべきで、「全ての責任を押し付けるべきではない」と主張しています。
チャン・タン・マン国会議長も、「村レベルが担えない場合は省が実施すべき」と述べ、テクノロジー支援、デジタルトランスフォーメーション(DX)、AI活用による支援の必要性を指摘しました。
実は、これが核心なんです。制度だけ変えて、実行するための人員・設備・予算を整備しないまま見切り発車しようとしている。これ、ベトナムの政策でよく見るパターンなんですよね…。
財務大臣の反論──理想論と現実のギャップ
財務大臣ニュエン・ヴァン・タン氏は、「行政区画の統合で管轄エリアが広がったため、省レベルでは物価変動に迅速に対応できない可能性がある。だから村レベルに任せる」と説明しています。
この理屈、一見正しいように聞こえます。確かに、現場に近い方が迅速に対応できる。でも、そもそも村レベルに対応能力がなければ、権限だけ渡しても意味がないんです。
タン大臣も「人員、設備、能力の向上が必要だ」と認めています。そして「政府は現在、村レベル職員の再配置・再教育を進めている。例えば来週から、財務省が基層レベルの財務・会計・予算業務の研修を実施する」と。
でも、ちょっと待ってください。法律を施行してから研修するんですか? 順序が逆じゃないですか?
これ、日本で例えると、「来月から市役所の窓口業務を町内会長に任せます。でも研修は再来月から始めます」みたいな話なんですよ。どう考えても無茶苦茶ですよね。
物価安定化の実務──想像以上に複雑
そもそも、物価安定化プログラムって何をするのか、皆さんご存知ですか?
ベトナムでは、政府が特定の生活必需品(米、食用油、砂糖、肥料など)の価格を一定範囲内に抑えるため、補助金を出したり、流通業者と協定を結んだりします。急激な物価上昇時には、国営企業や大手スーパーと協力して「安定価格商品」を供給するんです。
この業務、実際にはこんなことをやります:
- 市場価格のモニタリング: 毎日または毎週、市場・スーパー・小売店の価格調査
- 価格変動の分析: なぜ価格が上がったのか、需給、輸入価格、為替、季節要因などを分析
- 関係者との調整: 流通業者、小売店、生産者、物流会社などとの協議
- 補助金の配分: 誰にいくら補助するかの計算と実行
- 効果検証: 実際に物価が安定したかのチェック
これを0.6人の財務担当者ができると思いますか? しかも、彼らは他にも税務、予算管理、公共事業の会計など、山ほど仕事を抱えてるんです。
地方分権の理想と現実──ベトナムの構造的課題
実は、この問題の根っこには、ベトナムの地方分権政策の矛盾があります。
ベトナム政府は近年、「地方分権」「基層への権限移譲」を進めています。理屈としては正しい。中央集権では現場のニーズに迅速に対応できない、だから権限と予算を地方に移そうと。
でも、権限だけ移して、人員・予算・能力は移していない。これが問題なんです。
2024年7月に二層制を導入したのも、「行政の効率化」が目的でした。県レベルを廃止して、省と村の二層にすれば、意思決定が早くなる…はずでした。
ところが実際には、県レベルがやっていた業務を誰が引き継ぐのか、ちゃんと整理されないまま見切り発車しちゃったんです。その結果、村レベルが業務過多でパンク寸前、省レベルは管轄が広すぎて細かい対応ができないという、最悪の状況になりつつあります。
投資家として注目すべきポイント
さて、ここからはベトナム株投資家として、この問題をどう見るべきか考えてみましょう。
短期的な影響: 物価管理の混乱リスク
もしこの法改正が予定通り進み、村レベルが物価安定化の責任を負うことになったら、短期的には物価管理が混乱するリスクがあります。
特に、地方の農村部では、村レベルの行政能力がさらに低い。そうなると、急激な物価上昇が起きても、迅速に対応できない可能性があります。
これは、消費関連企業の業績に影響を与えるかもしれません。例えば:
- 小売業(MWG、FRTなど): 物価不安定→消費者の買い控え
- 食品・飲料(VNM、SABなど): 原材料価格の変動を価格転嫁しづらい
- 不動産(VHM、BCMなど): インフレ懸念→住宅ローン金利上昇
中長期的な影響: 行政効率化の遅れ
もっと根本的な問題は、行政改革の失敗リスクです。
ベトナムは今、「中所得国の罠」を抜け出すための重要な時期にあります。そのためには、行政の効率化、ビジネス環境の改善、インフラ整備など、政府の役割が非常に重要です。
ところが、こうした基本的な行政改革がうまくいかないと、外国投資家の信頼を損なう可能性があります。「ベトナムは改革のスピードが遅い」「政策の実行力が弱い」という評価が定着すると、FDI(外国直接投資)の流入が鈍化するかもしれません。
これは、**工業団地開発(BCM、KBCなど)や外資関連企業(GEX、KSBなど)**にとってはマイナス要因です。
ポジティブな見方: デジタル化・AI活用のチャンス?
一方で、チャン・タン・マン国会議長が指摘した「テクノロジー、DX、AI活用」というのは、実は大きなチャンスかもしれません。
もし政府が本気で、村レベルの行政をデジタル化し、AIで物価モニタリングや分析を自動化するなら、IT・テクノロジー企業にとっては追い風です。
例えば:
- FPT: 政府向けDXソリューション、AI導入支援
- CMG: 行政データ管理システム
- テック系スタートアップ: 価格モニタリングアプリ、AIアナリティクス
ベトナム政府は、こうした課題を「予算をかけずにテクノロジーで解決」しようとする傾向があります。だから、もしこの物価安定化の村レベル移管が本当に進むなら、行政DX関連のIT企業には大きなビジネスチャンスが生まれるでしょう。
まとめ: 制度改革の理想と現実のギャップ
今回の物価安定化責任の村レベル移管案、理想としては「現場に近い方が迅速に対応できる」というロジックは正しい。でも、現実には人員不足、能力不足、予算不足という三重苦が待ち受けています。
国会常務委員会の懸念は、まさに現場の実態を反映したもの。特にニュエン・タン・ハイ委員長の「村レベルが担えなければ省が実施すべき」という指摘は、極めて現実的です。
財務大臣は「研修を実施する」と言っていますが、それは法律を施行した後。順序が逆なんです。本来なら、研修を実施し、能力を高め、システムを整備し、それから法律を施行するべきなのに。
投資家としては、短期的には物価管理の混乱リスクを警戒しつつ、中長期的には行政DX関連のテクノロジー企業にチャンスがあると見ています。
ベトナムの政策って、こういうことがよくあるんです。理想は素晴らしいけど、実行段階でグダグダになる。でも、そのグダグダの中から、新しいビジネスチャンスが生まれることもある。そういう国なんですよね、ベトナムって。
いかがでしたでしょうか。今回の物価安定化の村レベル移管問題について、皆さんのご意見もぜひお聞かせください。コメント欄や@viettechtaroのDMでお待ちしています。
この記事が参考になったら、ぜひXでシェアしていただけると嬉しいです。より多くの方にベトナムの行政改革の実態を伝えたいと思っています。
【メンバーシップのご案内】
ベトナムの政策動向や投資への影響をより詳しく分析した記事は、メンバーシップで定期的にお届けしています。現地からのリアルタイム情報や、ポートフォリオの具体的な銘柄情報をお求めの方は、ぜひメンバーシップへのご参加をご検討ください。
https://note.com/gonviet/membership
一緒にベトナム株でFIREを目指しましょう!
【免責事項】
本記事の内容は、情報提供のみを目的としており、いかなる金融商品または仮想通貨への投資の推奨を意図するものではありません。ベトナム株式投資は価格の変動が大きく、リスクを伴う投資対象です。投資判断はご自身の責任に基づいて行ってください。本記事で提供される情報の正確性、完全性、または最新性については、最大限の注意を払っていますが、保証するものではありません。投資の際には、専門家への相談を推奨いたします。この記事は、法的、税務的、または財務的なアドバイスを提供するものではありません。本記事の情報に基づいて行われた投資による損失や損害について、執筆者および当ウェブサイトは一切の責任を負いません。株式投資およびその関連商品に投資する際は、各国の規制および法律を確認し、法令を遵守することが重要です。
#ベトナム株 #投資 #アジア株 #FIRE

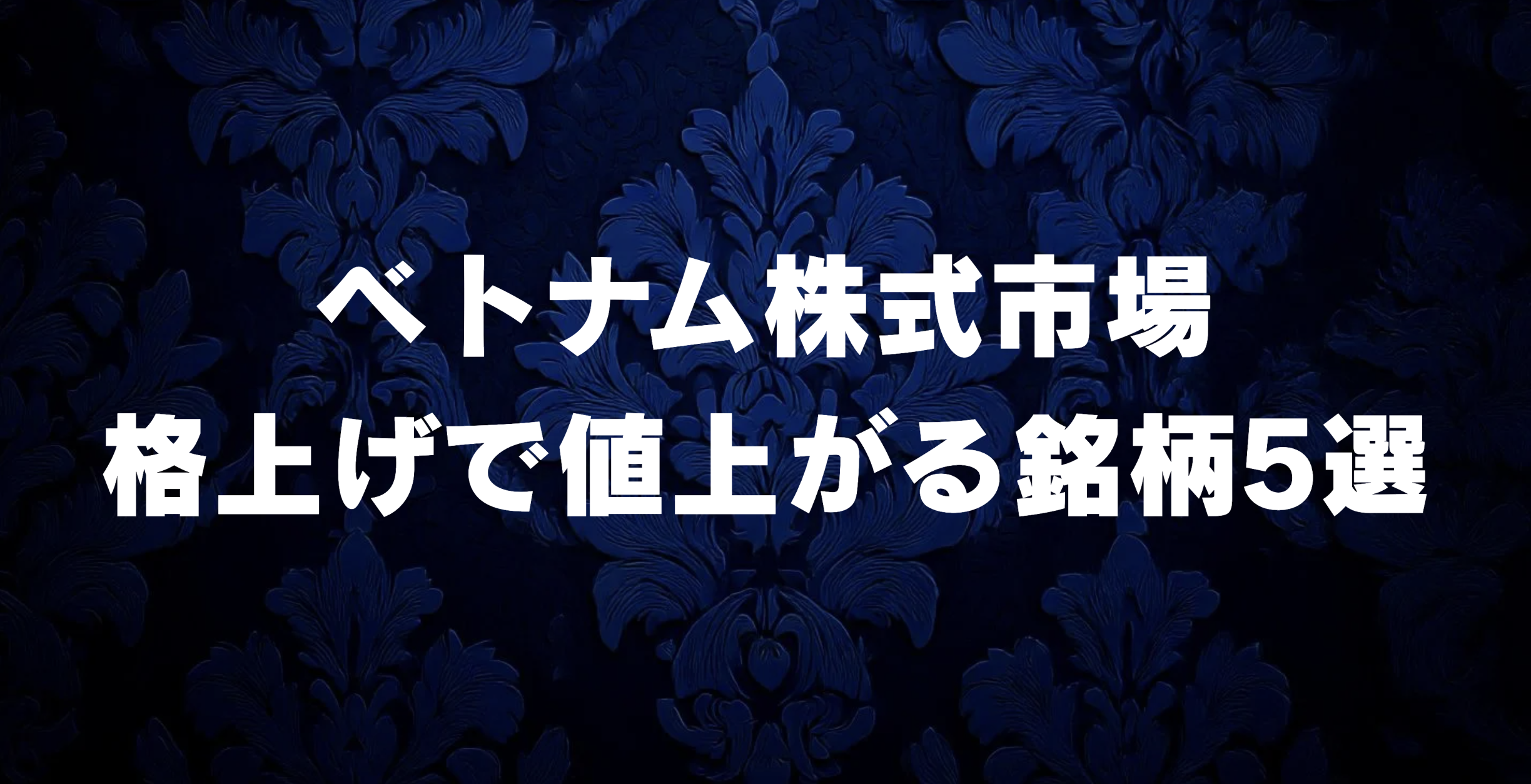











コメント