こんにちは、ベトナム総合ニュース&株式投資解説のベトテク太郎です。
ベトナムで働く日本人として、毎月の給与明細を見るたび、「この税金、ちょっと高くないか?」と感じていた方も多いのではないでしょうか。実は私も、ハノイで働き始めた頃、月収の中から差し引かれる個人所得税の額を見て、「もう少し手元に残れば生活が楽になるのに」と思ったものです。
そんな中、ベトナム政府が2025年11月に発表した個人所得税法の改正案が、大きな注目を集めています。この改正、単なる数字のいじりではありません。ベトナムで働く私たちの手取り収入を増やし、生活の質を向上させる可能性を秘めた、かなり本気の税制改革なんです。
今回は、この個人所得税改正がベトナム経済と私たちの暮らしにどんな影響を与えるのか、グエン・クアン・フイ氏(グエン・チャイ大学財政・銀行学部CEO)へのインタビュー記事をもとに、詳しく解説していきます。
2026年から適用される基礎控除額の大幅引き上げ
まず押さえておきたいのが、2026年1月1日から適用される基礎控除額の引き上げです。現行の月額1,100万VND(約6万6,000円)から、なんと1,550万VND(約9万3,000円)へと、約41%もの大幅アップが決定しました。
これ、数字だけ見ると「ふーん、そうなんだ」で終わってしまいそうですが、実際の影響は相当大きいんです。
扶養家族の控除額も、現行の440万VND(約2万6,400円)から620万VND(約3万7,200円)に引き上げられます。財政省の試算によると、この改正で現在最低税率区分で納税している210万人以上が、所得税の納税対象外になるとのこと。つまり、これまで税金を払っていた人の多くが、丸々その分を手元に残せるようになるわけです。
私の周りのベトナム人スタッフたちも、この話題で持ちきりです。ハノイのタイ湖エリアにあるカフェで先日聞いた話では、月収2,000万VND(約12万円)程度の若手エンジニアが「これで毎月の生活費にもう少し余裕ができる」と喜んでいました。
個人所得税改正の最大のポイントとは
グエン・クアン・フイ氏のインタビューで最も印象的だったのが、「基礎控除額の引き上げこそが、今回の改正で最も重要な変更点だ」という指摘です。
なぜこれがそんなに重要なのか。フイ氏は「生活費の上昇が名目所得の伸びを上回っている現実を反映した、社会的意義のある政策調整だ」と説明しています。
ベトナムに住んでいると、この言葉の意味が痛いほどわかります。ハノイの物価は毎年確実に上がっています。私がよく行くロンビエン地区の市場でも、野菜や肉の価格がじわじわと上昇しているんです。給料は上がっても、実際に使えるお金が増えた実感がない。そんな状況を、今回の改正は直接的に改善しようとしているわけです。
特に中低所得層にとって、この変更は家計に直接的な「ゆとり」をもたらします。月収2,000万〜2,500万VND(約12万〜15万円)の層では、納税額が大幅に減少し、その分を生活必需品の購入や教育費に回せるようになります。
フイ氏の言葉を借りれば、「一部の所得が課税対象から外れ、労働者の手元に残る」ことで、「家計の財政的スペースが広がり、必需品への支払い能力が向上し、家計の福祉が強化され、経済的プレッシャーが軽減される」というわけです。
税率区分の簡素化がもたらす実質的メリット
改正案のもう一つの重要なポイントが、税率区分の簡素化です。現行の7段階から5段階へと削減され、各段階間の所得幅も拡大されます。
これ、一見すると「計算が楽になるだけ?」と思うかもしれませんが、実は働く人たちのモチベーションに直結する大きな変更なんです。
現行の7段階制度では、所得がわずかに増えただけで次の税率区分に「ジャンプ」してしまい、納税額が急増するという問題がありました。フイ氏はこれを「昇給や昇進時に『罰せられている』ような感覚」と表現していますが、まさにその通りなんです。
私自身、数年前に昇給したとき、喜びも束の間、次の月の給与明細を見て「あれ、思ったほど手取りが増えてない」とがっかりした経験があります。これ、税率区分のジャンプが原因だったんですよね。
5段階制度と所得幅の拡大により、この「バッファーゾーン」が生まれます。所得が合理的に増加しても、すぐに税率区分が上がらないため、「頑張って働いて収入を増やそう」というモチベーションが保たれるわけです。
昇進や昇給を躊躇する心理が解消され、生産性向上への明確なインセンティブが生まれる。これは個人にとっても、企業にとっても、そしてベトナム経済全体にとっても、プラスの影響をもたらすはずです。
教育費・医療費控除の社会的意義
改正案で注目すべき第三のポイントが、控除対象の拡大、特に教育費と医療費の控除です。
フイ氏はこれを「長期的な社会的ビジョンを持った改革の最も明確な点の一つ」と評価しています。なぜか。これらは必需的支出であり、通常、家計予算の大きな割合を占めるからです。
ハノイに住んでいると、教育にかける家庭の熱意と負担の大きさを日々感じます。私の知り合いのベトナム人家族は、子供をインターナショナルスクールに通わせるため、月収の30%以上を学費に充てています。医療費も同様で、公立病院の混雑を避けて私立クリニックを利用すると、それなりの出費になります。
この控除拡大は「二重の効果」をもたらすとフイ氏は指摘します。
社会的には、小さな子供がいる家庭や、高齢者や病人の世話が必要な家庭の負担が即座に軽減されます。ロッテセンター近くのオフィスで働く30代の同僚は、「子供の学費が控除対象になれば、家計がかなり楽になる」と期待を寄せていました。
経済的には、これは巧妙なテコ入れ策です。これらの費用の控除を認めることで、政府は教育と医療への民間投資を間接的に強く奨励しているのです。
人々の税負担が軽減されると、高品質なサービスを選択する動機と財政的能力が生まれます。それが市場需要を創出し、民間の教育機関や医療機関の発展を促進する。教育と医療という、国の人的資源の質と競争力を決定づける二つの重要分野の発展につながるというわけです。
フイ氏の言葉を借りれば、これは社会福祉政策における思考の転換であり、「事後補助」(国が税金を徴収してから公共システムを通じて再配分する)メカニズムから「事前負担軽減」、つまり人々が収入を保持して自ら財政計画を立て、サービスを選択し、自分自身の福祉を確保できるようにする、持続可能なアプローチへの移行なんです。
個人消費の拡大と経済成長への波及効果
さて、ここまで個人や家計へのメリットを見てきましたが、この改正がベトナム経済全体にどう影響するのか、という点も重要です。
フイ氏は「数百万人の納税者がより多くの所得を手元に残せるようになると、その経済的影響は個人レベルに留まらず、社会全体に波及する」と指摘しています。
基礎控除の引き上げと税率区分の拡大の本質は、資金の再配分です。予算に集中していた資源が家庭部門、つまり最も消費性向が高い部門に移転されるわけです。
短期的には、人々の手元に増えた資金が、商業、サービス、消費財生産に直接的な「刺激」を与えます。店舗、レストラン、工場が購買力の増加を実感するでしょう。私がよく行くタイ湖周辺のレストランでも、「客の財布のひもが緩くなれば売上が伸びる」という期待の声を聞きます。
中期的には、安定した購買力が市場の信頼を強化し、企業が輸出だけでなく国内産業への投資を大胆に行うよう促し、よりバランスの取れた発展を生み出します。
予算的には、個人所得税収の減少という財政的影響は予測されています。しかし、期待される経済・社会的な波及効果が、これをかなりの程度補うと見込まれているのです。
フイ氏の説明が分かりやすいので引用します。「経済は循環的に機能します。人々の消費が増えると、企業の売上がそれに応じて増加します。それが生産の拡大につながり、結果として、間接税や法人所得税からの国の税収もその循環に応じて増加するのです」
つまり、短期的には税収が減っても、消費拡大→企業業績向上→生産拡大→新たな税収増という好循環が期待できるというわけです。ベトナム政府は、この「先行投資」的な発想で改正に踏み切ったと言えるでしょう。
ベトナム株投資家としての視点
ベトナム株投資家として、この税制改正をどう見るか。私の結論は「かなりポジティブ」です。
まず、個人消費の拡大が期待できるという点。ベトナム経済において、内需の成長は非常に重要です。これまで輸出依存が強かったベトナムですが、1億人の人口を抱える国として、内需主導の成長モデルへの転換が進んでいます。
今回の税制改正で購買力が高まれば、小売、外食、娯乳、教育、医療といった内需関連セクターの企業にとって追い風になります。私のポートフォリオにも、ベトナムの小売大手や消費財メーカーが含まれていますが、これらの業績にプラスの影響が出る可能性が高いと見ています。
特に注目しているのが、MWG(モバイルワールド)やFPT(FPT株式会社)といった、中間層の消費拡大から恩恵を受けやすい企業です。手取り収入が増えれば、家電やIT製品、教育サービスへの支出も増えるでしょう。
また、医療費控除の拡大は、民間医療セクターの成長を後押しします。ベトナムの医療市場は急成長しており、中間層の拡大とともに、質の高い民間医療への需要が高まっています。このトレンドが税制面からも支援されることになります。
教育費控除も同様です。ベトナムの親は子供の教育に非常に熱心で、質の高い教育サービスへの需要は旺盛です。FPTのような教育事業も展開している企業にとっては、さらなる成長の機会となるでしょう。
もちろん、短期的には政府の税収減少という懸念もあります。しかし、フイ氏が指摘するように、消費拡大から生まれる間接税や法人税の増収で、中長期的には補われる可能性が高いと考えています。
改正案の今後のスケジュールと注目ポイント
今回の基礎控除額引き上げは、国会常任委員会で決定され、2026年1月1日から適用されることが確定しています。
一方、税率区分の簡素化(7段階→5段階)や、教育費・医療費控除の拡大といった、より大きな改革については、「個人所得税法(改正)草案」として、現在開催中の第10回国会会期で議論される予定です。
この草案の最大の突破口は、納税者が税金を計算する前に、実際の必要経費を控除できるようにするという提案です。多くの省庁、銀行、国会代議員団が、控除対象の拡大、特に医療、教育、住宅、交通という人々の最も重い4つの負担に焦点を当てた提案を行っています。
住宅ローンの利息や通勤費用まで控除対象になれば、これは本当に画期的な改革です。ハノイの不動産価格は年々上昇しており、住宅ローンを抱える人にとっては大きな負担軽減になります。
ただし、草案が国会で承認されるかどうかはまだ不透明です。控除範囲の拡大は納税者にとっては朗報ですが、政府の税収への影響も大きいため、慎重な議論が必要です。
今後の国会審議の動向を注視していく必要がありますね。承認されれば、ベトナムの税制は大きく変わり、私たちの生活や投資環境にも大きな影響を与えることになります。
まとめ:生活の質向上と経済成長の両立を目指す改革
2026年から始まるベトナムの個人所得税改正は、単なる税制のいじりではなく、国民の生活の質向上と経済成長の両立を目指す、本格的な改革だと言えます。
基礎控除額の41%引き上げは、中低所得層の家計に直接的なゆとりをもたらし、税率区分の簡素化は働く人々のモチベーションを高め、教育費・医療費控除の拡大は人的資本への投資を促進します。
そして、これらが総合的に作用することで、個人消費が拡大し、内需主導の経済成長が加速する。短期的な税収減を上回る、中長期的な経済・社会的効果が期待されているわけです。
ベトナム株投資家としても、この改革はポジティブに捉えています。内需関連セクターの成長加速が見込まれ、特に小売、外食、教育、医療といった分野の企業に注目しています。
ベトナムに住み、ベトナム株に投資する者として、この改革がどう展開していくのか、そして私たちの暮らしと投資にどんな影響をもたらすのか、今後も注視していきたいと思います。
いかがでしたでしょうか。今回の個人所得税改正について、皆さんのご意見もぜひお聞かせください。コメント欄や@viettechtaroのDMでお待ちしています。
この記事が参考になったら、ぜひXでシェアしていただけると嬉しいです。より多くの方にベトナム投資の魅力を伝えたいと思っています。
【メンバーシップのご案内】 より詳細な投資分析や、ポートフォリオの具体的な銘柄情報、現地からのリアルタイム情報をお求めの方は、ぜひメンバーシップへのご参加をご検討ください。 https://note.com/gonviet/membership
一緒にベトナム株でFIREを目指しましょう!
【免責事項】 本記事の内容は、情報提供のみを目的としており、いかなる金融商品または仮想通貨への投資の推奨を意図するものではありません。ベトナム株式投資は価格の変動が大きく、リスクを伴う投資対象です。投資判断はご自身の責任に基づいて行ってください。本記事で提供される情報の正確性、完全性、または最新性については、最大限の注意を払っていますが、保証するものではありません。投資の際には、専門家への相談を推奨いたします。この記事は、法的、税務的、または財務的なアドバイスを提供するものではありません。本記事の情報に基づいて行われた投資による損失や損害について、執筆者および当ウェブサイトは一切の責任を負いません。株式投資およびその関連商品に投資する際は、各国の規制および法律を確認し、法令を遵守することが重要です。
#ベトナム株 #投資 #アジア株 #FIRE

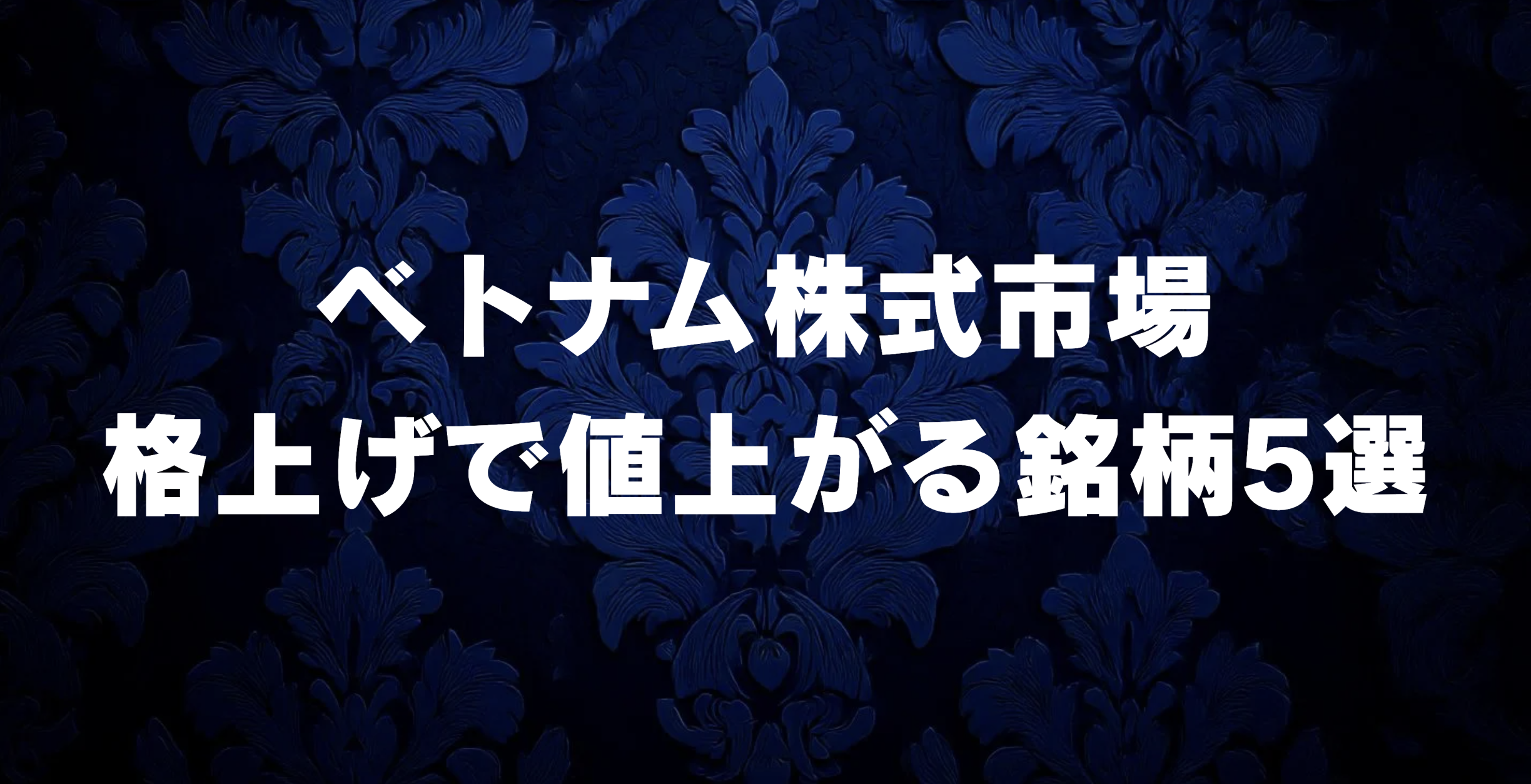











コメント