こんにちは、ベトナム総合ニュース&株式投資解説のベトテク太郎です。
米トランプ政権の関税政策が再び世界経済を揺さぶる中、新興国市場への影響が懸念されています。しかし、リスク分析会社Verisk Maplecroft社の最新調査によると、ベトナムを含む多くの新興国は、予想以上に米国の関税に対する耐性を持っていることが明らかになりました。
ハノイで生活していると、ベトナム経済の底力を肌で感じることが多いのですが、今回の調査結果はまさにそれを裏付けるものでした。タイ湖エリアのカフェで現地ビジネスマンと話していても「米国一辺倒の時代は終わった」という声をよく聞きます。今回は、この調査結果を詳しく分析し、ベトナム株投資家にとって何を意味するのか考察していきます。
新興国20カ国の耐性分析:ベトナムは上位グループに
Verisk Maplecroft社は、世界の主要新興国20カ国を対象に、債務水準から輸出収益への依存度まで、複数の指標を分析しました。その結果、中国、ブラジル、インドといった大国を含む多くの新興国が、米国の関税措置に対して「予想以上の耐性」を持つことが判明しました。
注目すべきは、ベトナムとメキシコが「米国貿易への依存度が最も高いグループ」に分類されながらも、「経済回復力の高い国々」にも同時に含まれている点です。
これは一見矛盾しているように思えますが、実は重要なポイントです。ベトナムは確かに米国向け輸出が多いものの、以下の要因により、関税リスクに対する耐性が強化されています。
- 経済支援政策の充実:政府による積極的な産業支援と投資誘致
- インフラの急速な改善:港湾、道路、電力網の整備が加速
- 政治的安定性:共産党一党体制による政策の一貫性
実際、ハノイのタンロン工業団地を訪れると、外資系企業の工場が次々と建設されている様子が見られます。これは単に人件費の安さだけでなく、ベトナム政府の産業政策が評価されている証拠でしょう。
「第三の市場」戦略:米中依存からの脱却
調査の共同執筆者であるReema Bhattacharya氏は、新興国の戦略について興味深い指摘をしています。
「ほぼすべての新興国市場は、米国と中国の両方とビジネスをする必要があることを理解していますが、どちらにも過度に依存することはできません。そのため、第三の市場が必要なのです」
これはベトナムにも完全に当てはまります。ベトナムの貿易データを見ると、この戦略が明確に表れています。
米国向け輸出は確かに大きな比重を占めていますが、同時にEU、日本、韓国、ASEAN諸国との貿易も着実に拡大しています。特に、CPTPP(環太平洋パートナーシップ協定)やEVFTA(EU・ベトナム自由貿易協定)といった多国間協定を積極的に活用し、輸出先の多様化を進めているのです。
ロッテセンターハノイで開催される貿易セミナーに参加すると、ベトナム企業が東南アジア市場や中東市場への進出を本格化させている様子がよく分かります。「米国市場は重要だが、そこだけに頼るのはリスク」という認識が、ベトナムのビジネス界で共有されているのです。
BRICS諸国間の貿易拡大:新たな経済圏の形成
報告書では、BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)諸国間の貿易が「著しく増加している」と指摘されています。ベトナムは正式なBRICSメンバーではありませんが、この動きは間接的に大きな影響を与えています。
中国との経済関係を見ると、ベトナムは巧みなバランス外交を展開しています。中国からの原材料輸入を活用しながらも、完成品を欧米やASEAN諸国に輸出するという「加工貿易モデル」を確立しているのです。
さらに注目すべきは、報告書が指摘する「人民元の国際化」です。ブラジル、アルゼンチン、チリが中国人民銀行との現地通貨決済協定に署名し、中国国有企業がラテンアメリカのリチウムや銅の採掘プロジェクトに融資しています。
ベトナムも同様の動きを見せており、中国との貿易で人民元決済を増やしています。これは米ドル依存度を下げ、為替リスクを分散する戦略でもあります。
中国:「代替不可能な製造大国」としての地位
報告書は中国について特に詳しく分析しています。米中地政学的緊張の影響を特に受けやすい立場にありながら、中国は「あまりにも深く根を張っているため、他の場所で複製することはほぼ不可能」と評価されています。
その理由は以下の通りです。
- 多様な輸出基盤:あらゆる産業分野で競争力を持つ
- 豊富な人材:エンジニアから熟練工まで層が厚い
- 完成されたサプライチェーン:部品調達から最終組立まで国内で完結
しかし、10月の輸出データは厳しい現実を示しました。トランプ大統領の再選後、中国の輸出は2025年2月以降で最悪の落ち込みを記録したのです。
ベトナムにとって、これは大きなチャンスでもあります。「チャイナ+1」戦略を進める多国籍企業が、中国からベトナムへ生産拠点を移管する動きは今後も続くでしょう。実際、ハノイ郊外の工業団地では、中国から移転してきた台湾系や韓国系企業の工場建設が相次いでいます。
ベトナム株投資家への示唆:長期的な成長トレンドは不変
今回の分析結果は、ベトナム株の長期投資家にとって非常にポジティブな内容です。重要なポイントをまとめると、以下のようになります。
米国関税リスクへの耐性が証明された: ベトナムは米国貿易への依存度が高いものの、経済政策、インフラ、政治安定性により、関税措置に対する耐性が強い。これは、短期的な市場変動があっても、長期的な成長トレンドは維持される可能性が高いことを意味しています。
輸出先の多様化が進展: 「第三の市場」戦略により、米中どちらにも過度に依存しないバランスの取れた貿易構造が構築されつつある。これは、地政学リスクの分散につながります。
FDI流入の継続が期待できる: 中国からの生産移管トレンドは継続し、ベトナムへの外国直接投資は今後も堅調に推移する見込み。これは製造業、不動産、インフラ関連銘柄にとって追い風となります。
FTSE新興国市場への昇格の意義: 2026年9月に予定されているFTSE新興国市場への昇格は、ベトナム経済の「耐性」と「成長性」が国際的に認められた証でもあります。昇格後は、より多くの機関投資家資金の流入が期待できます。
私の保有するベトナム株ポートフォリオでは、この「耐性」を重視した銘柄選定を心がけています。具体的には、輸出先が多様化している企業、国内需要も取り込める企業、FDI増加の恩恵を受ける企業を中心に構成しています。
ビングループ「VIC」のような不動産・小売複合企業、FPT「FPT」のようなIT企業、ホアファットグループ「HPG」のような鉄鋼企業など、ベトナムの内需と外需の両方を取り込める銘柄が、長期的には最も安定したリターンをもたらすと考えています。
まとめ:新興国投資の新時代
米国の関税政策は確かに世界経済に波乱をもたらしますが、今回の調査が示すように、新興国市場は以前よりもはるかに強靭になっています。特にベトナムは、その典型例と言えるでしょう。
ハノイで生活していて感じるのは、ベトナムの人々と政府が「外部環境の変化に柔軟に対応する力」を持っているということです。米中対立が激化すれば、その隙間を巧みに突いて成長機会を掴む。これがベトナムの強みなのです。
短期的には株価の変動もあるでしょうが、長期的な視点で見れば、ベトナム株は依然として魅力的な投資対象です。今回の調査結果は、その確信をさらに強めてくれました。
いかがでしたでしょうか。今回のベトナムの関税耐性分析について、皆さんのご意見もぜひお聞かせください。コメント欄や@viettechtaroのDMでお待ちしています。
この記事が参考になったら、ぜひXでシェアしていただけると嬉しいです。より多くの方にベトナム投資の魅力を伝えたいと思っています。
【メンバーシップのご案内】 より詳細な投資分析や、ポートフォリオの具体的な銘柄情報、現地からのリアルタイム情報をお求めの方は、ぜひメンバーシップへのご参加をご検討ください。 https://note.com/gonviet/membership
一緒にベトナム株でFIREを目指しましょう!
【免責事項】 本記事の内容は、情報提供のみを目的としており、いかなる金融商品または仮想通貨への投資の推奨を意図するものではありません。ベトナム株式投資は価格の変動が大きく、リスクを伴う投資対象です。投資判断はご自身の責任に基づいて行ってください。本記事で提供される情報の正確性、完全性、または最新性については、最大限の注意を払っていますが、保証するものではありません。投資の際には、専門家への相談を推奨いたします。この記事は、法的、税務的、または財務的なアドバイスを提供するものではありません。本記事の情報に基づいて行われた投資による損失や損害について、執筆者および当ウェブサイトは一切の責任を負いません。株式投資およびその関連商品に投資する際は、各国の規制および法律を確認し、法令を遵守することが重要です。
#ベトナム株 #投資 #アジア株 #FIRE

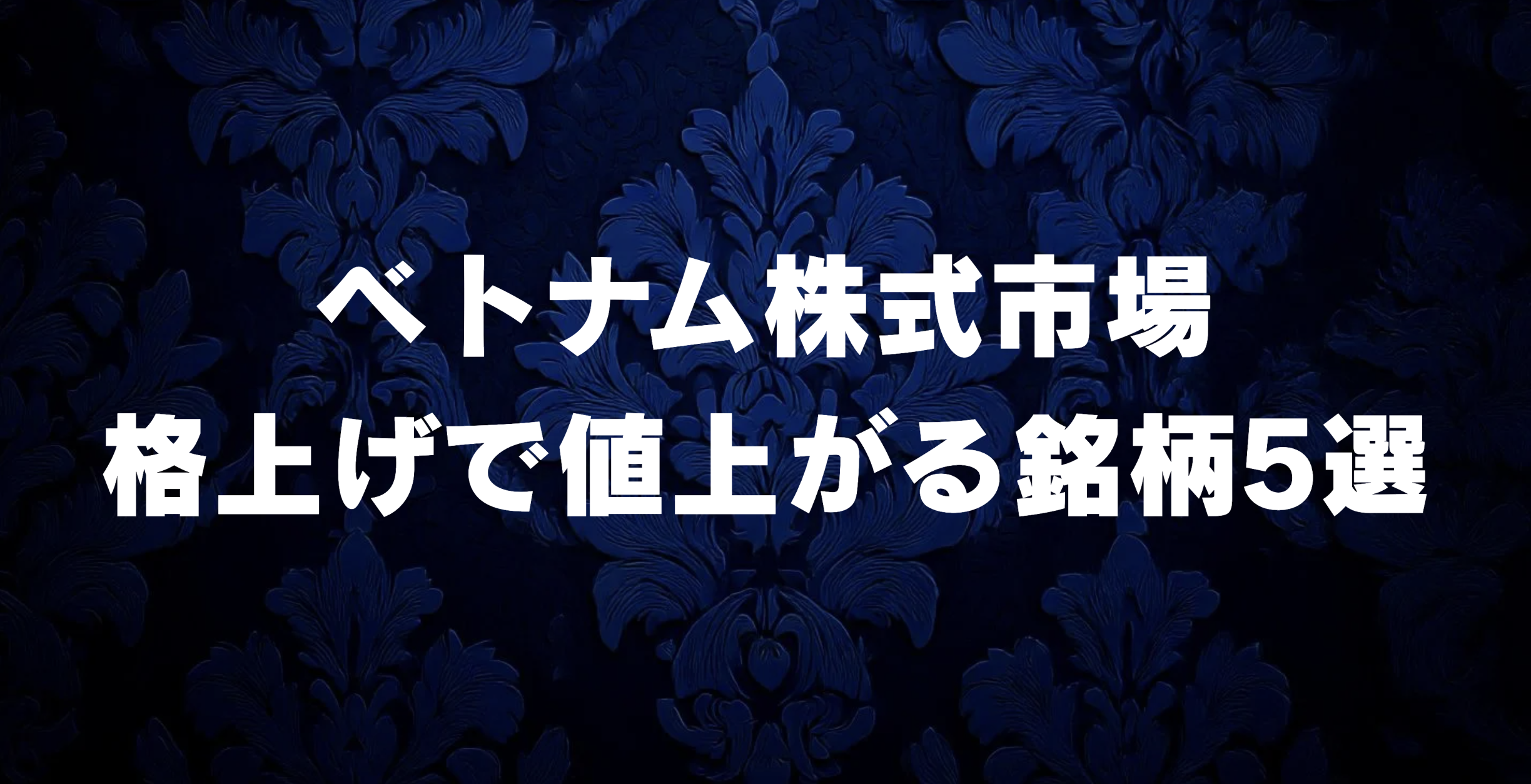











コメント